その日は怖い鬼部長がいる日だったのでどうしても早めに出社しなければならなかったのですが、バタバタしていて結構きわどい時間に家を出たんです。駅までジャスト徒歩10分の距離なんですが、男性にも負けないくらい早足で歩いたらなんと最高記録を樹立、7分で駅までつきました。
やればできるよ、と思いながらホッとして電車に乗り、読み終わりかけのアーヴィングの本を開いた瞬間すぐに夢中になってしまい、気付くと降りるはずの駅を飛ばしてして結局遅刻してしまいました(もうやだ・・・)。
以前オースターのレビューの時に挙げた『ついうっかり次の駅まで行っちゃったほど熱中した作家』ランキングは下記のようになっております。
今回も確かに裏付けられました。
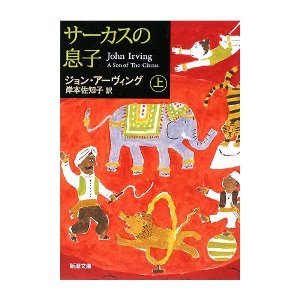
(あらすじ)
舞台はインド、ボンベイ。
彼はカナダに住むインド人医師のファルークはサーカスの小人の遺伝子を研究するために時々故郷のボンベイへ行ったり来たりの生活を続けている。ある日、彼も足繁く通う会員制クラブ「ダックワースクラブ」で謎の殺人事件が起こった。その謎を追いかけて、ファルークを慕うタフな小人のブィノド、アメリカ人のヒッピーで訳あってボンベイへ流れついた美女ナンシー、生き別れた双子の兄弟ダーとマーティン、路上で盗みを繰り返す不具の孤児などが織り成すヒューマンドラマとサスペンスコメディー。
舞台はインド、ボンベイ。
彼はカナダに住むインド人医師のファルークはサーカスの小人の遺伝子を研究するために時々故郷のボンベイへ行ったり来たりの生活を続けている。ある日、彼も足繁く通う会員制クラブ「ダックワースクラブ」で謎の殺人事件が起こった。その謎を追いかけて、ファルークを慕うタフな小人のブィノド、アメリカ人のヒッピーで訳あってボンベイへ流れついた美女ナンシー、生き別れた双子の兄弟ダーとマーティン、路上で盗みを繰り返す不具の孤児などが織り成すヒューマンドラマとサスペンスコメディー。
1)アーヴィングの魅力
アーヴィングの作品は一貫的に共通して言えることなのですが、前半はもう辛抱の連続です。
外国文学慣れしていない人だと嫌になって飽きてポイする危険性が高いくらい、ダラダラしています。
外国文学慣れしていない人だと嫌になって飽きてポイする危険性が高いくらい、ダラダラしています。
だけど不思議なのは読み進めていくうちに、この個性的な登場人物にとてつもない愛着を感じ始め、ページを開くたびに何か親しさが湧いてきて、この先がどう展開していくのが見守るような温かい気持ちになってきます。
そして彼らに何かが起こると、一緒に狼狽し、感嘆し、怒り笑い時には涙を流すほど感情移入してきます。
あんなに退屈だった本に異様な愛着を感じ始めたらもうそれはジョン・アーヴィングという作家の魔法にかかっている証拠です。
2)「インターナショナル」
作者があとがきで「これはインドについての小説ではない」と何度も述べているように、この本は舞台がインドなだけで視点はもっと別のところに置かれています。
カナダに戻っていたある日、ファルークは仕事の用事を済ませ帰宅するため一台のタクシーに乗る。
すると運転手がたまたまどうしようもない若者で、ファルークの肌の色や風貌を意地悪くからかいます。挙句の果てには目的地とは反対方向に車を走らせ、インド人街のど真ん中に彼を放り出されて最後にこう叫ぶ。
すると運転手がたまたまどうしようもない若者で、ファルークの肌の色や風貌を意地悪くからかいます。挙句の果てには目的地とは反対方向に車を走らせ、インド人街のど真ん中に彼を放り出されて最後にこう叫ぶ。
Go Home!
どうしようもない疲労感に襲われながらファルークはそれまで足を一度も踏み入れたことのないインド人街をたどたどしく歩く。ショーウィンドウにはサリーを着た古ぼけたマネキンが飾られ、ガラムマサラの匂いがどこからか漂ってくる。インド人でありながらも紆余曲折を辿りながらその地にたどり着いたファルークはおそらくこう考えたに違いない。
「わたしは一体どこ(home)に属しているんだろうか」
胸を打たれたシーンでした。
この本のテーマとしてまず挙げられるのは、『移民としてのアイデンティティー』というのが大きなキーであることはまず間違いありません。インド人として生まれ、ヨーロッパに暮らし、カナダに永住権を得、英語も堪能に操り職業も医師であるファルーク。しかし彼はボンベイに帰ってもどこかしっくりこない違和感を覚え、カナダに戻ってもそこは故郷ではない。どんなに普通に振舞ってもそこには境界線があるのです。
(本文抜粋:)
彼は大人になってからの大部分を自分は本当のインド人ではないという居心地の悪さと共に(インドにいる時は特にそうだった)生きてきた。これから先トロントで、本当はカナダに同化しきれていないという居心地のわるさを抱えつつ生きていくのはいったいどんな気分だろう。彼はカナダ国民だったが自分が真のカナダ人でないことを知っていた。これから先も、完全に「同化」できたと感じることはないであろう。「移民は死ぬまで移民だ!」父ラウジのきつい一言を、彼は永遠にひきずって生きていくことになるのだろう。人間、そういう否定的な断言を下されると、頭ではそれを否定していても結局はずっと後までそれを忘れられないものだ。あまりにも強烈に植えつけられてしまった概念は、ついには目で見える、実質をともなった物体と化してしまう。
たとえば、人種差別的な言葉がそうだ。
それを投げつけられた時の踏みにじられた自尊心の痛みはけっして忘れられるものではない。それらに遭遇するたびに彼は自分がいかに社会の周縁部に属する人間であるかをさまざまと思い知らされる気がした。
たとえば、人種差別的な言葉がそうだ。
それを投げつけられた時の踏みにじられた自尊心の痛みはけっして忘れられるものではない。それらに遭遇するたびに彼は自分がいかに社会の周縁部に属する人間であるかをさまざまと思い知らされる気がした。
昔ある人から「インターナショナル」の意味を教えてもらったことがあります。
インター(Inter=中間の)、ナショナル(国、国民)
つまりインターナショナルとはどっちに依存することもない、中間的な立場のことを意味していると。
教えてくれた人はそう言ってました。
インターナショナルというのはけして働くビジネスマンだけを指すのではなく、華僑と呼ばれる中国人やこの本の主人公のようなインド人、アフリカ人、ロシアや東欧の人々なども含まれます。そのヒエラルキーの一つのレイヤーの中に属する彼らのような人々の心の隙間を、アーヴィングはファルークという登場人物になぞらえて実に見事に表現しています。
教えてくれた人はそう言ってました。
インターナショナルというのはけして働くビジネスマンだけを指すのではなく、華僑と呼ばれる中国人やこの本の主人公のようなインド人、アフリカ人、ロシアや東欧の人々なども含まれます。そのヒエラルキーの一つのレイヤーの中に属する彼らのような人々の心の隙間を、アーヴィングはファルークという登場人物になぞらえて実に見事に表現しています。
3)キャラバン的、自由の代償
(本文抜粋:双子の片割れ、マーティンがインドを出て行くときのセリフ)
いつも何ていうか、こそ泥みたいに逃げ出していくんです。信じてくれた人たちに小さな迷惑をかけては消えていく。私なんてせいぜいそんなものです。私が自分に対して抱く感じだって似たようなものです。失望とか、挫折感とか、そんなドラマチックな感情じゃない。ただ、ちらっと胸をかすめては消えていく、小さな屈辱感があるだけです
なんだかエコーのようにこだまするセリフでした、私にとっては。
実際に同じことがあったとかないとかそういうことじゃなく、
似たような空気を感じた経験がおそらくいつかどこかにあるからなんだと思います。
似たような空気を感じた経験がおそらくいつかどこかにあるからなんだと思います。
この言葉に対してファルークは、「信じられる場所や拠りどころが心のどこかにあればきっと迷わない」
そんなふうに伝えています。
確かに、そういうよりどころは大事なんでしょうね。結局のところそういうことなんでしょうね。
キャラバンな生き方だろうとなんだろうと。
4)雪の夜、啓示
このラスト、数十ページはとんでもないくらいに感動的でした。
アーヴィングはそんなファルークの思いを、実に美しく静かで感動的に決着させました。
このラストを読まずしてこの「サーカスの息子」の意義はないと断言できるほど。
私はここの最後を読みながらうっすら涙が浮かんできたほどでした(そして遅刻しちゃったんですが)。
アーヴィングはそんなファルークの思いを、実に美しく静かで感動的に決着させました。
このラストを読まずしてこの「サーカスの息子」の意義はないと断言できるほど。
私はここの最後を読みながらうっすら涙が浮かんできたほどでした(そして遅刻しちゃったんですが)。
ある雪の降る夜、妻と待ち合わせた通りへ向かうファルークはある親子に出会う。
頼りない街灯の下を歩く親子からみたら、灯りの外を一人歩く肌の黒いインド人を怪しく不信に思うだろう。
降る雪を口をパクパクさせながら踊るように歩く子供があまりにもかわいくて思わず微笑んだファルークを見て、その母は一瞬怯えた様子を見せる。彼女からしたらマフラーと帽子の隙間から見えるギョロリとした目がとてつもなく怪しく危険な男に映ったに違いない。
降る雪を口をパクパクさせながら踊るように歩く子供があまりにもかわいくて思わず微笑んだファルークを見て、その母は一瞬怯えた様子を見せる。彼女からしたらマフラーと帽子の隙間から見えるギョロリとした目がとてつもなく怪しく危険な男に映ったに違いない。
母親は子供の肩を抱く力を少しだけ強め、かばうようにそそくさとその場を立ち去ろうとする。
その時子供が母親の一瞬の隙を狙って彼女をかわし、街灯を外れて通りの端を歩くファルークのそばへ無邪気にかけよってきた。
そしてこう尋ねた。
「おじさんはどこの人なの?」
あまりにも純真な子供の姿を目の前にして、彼は今までのようにいろんな回答を選択することができた。
だけど今までそれらのどの回答に対しても一度もしっくりときたことがなかった。
ましてやこの純粋な子供を目の前にして間違ったことを言いたくなかった。
ましてやこの純粋な子供を目の前にして間違ったことを言いたくなかった。
それに対して彼が出した最後の答えとは・・・。

一枚の絵がありありと目の前に浮かんでくるような、実に印象的で美しいラストにはため息がでそう。
何より私はファルークが出した言葉によって、
彼自身がようやくいろんなしがらみから解放されたことに感動しました。
彼自身がようやくいろんなしがらみから解放されたことに感動しました。
薄暗い街灯がまるでスポットライトのようにささやかに彼を照らし出すその後ろ姿。
ジーンとしちゃいました。
いや~・・・最高のラストでした。
アーヴィングが好きな理由はこういうところなんですよね。人間味があるっていうか。
では長くなりましたがこの辺で。
アディオス。
追伸:鬼部長はその日直行でした。