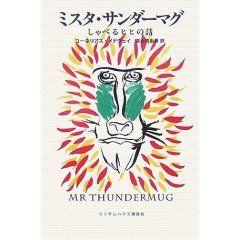
ある町にヒヒがやってくる。
ヒヒは流暢にヒトの言葉を話す。スルスルと、それはまるで毛糸玉がほぐれていくようにとても自然だ。
彼はどこからやってきたのか、またなぜヒトの言葉を話すのか、誰も知らない。
ヒヒは流暢にヒトの言葉を話す。スルスルと、それはまるで毛糸玉がほぐれていくようにとても自然だ。
彼はどこからやってきたのか、またなぜヒトの言葉を話すのか、誰も知らない。
彼は窓越しから覗き見たテレビ番組からある言葉を覚えた。
「ミスタ・サンダーマグ(Mr.thunder mug=おまる)」
それが、彼が自ら自分につけた名前だ。
「ミスタ・サンダーマグ(Mr.thunder mug=おまる)」
それが、彼が自ら自分につけた名前だ。
ミスタ・サンダーマグの顔の骨はもともと長くできており、滑稽なほど悲しげなヴィクトリア朝の貴族を思わせる。彼は廃墟となった空き家に家族(もヒヒ)と住み着いた。ゴキブリがたくさん出るから市役所がいずれ処置をほどこさねばならないその廃墟は、サンダーマグには格好の住みかとなった。なぜならゴキブリは、彼らにとって貴重な食糧だったからだ。お腹が空いたら食べちゃえばいいのである。
そんなある日、市役所の住宅課のフォレストさんが訪ねてくる。
その家に住んでいる事自体が不法侵入であると言うのだ。
その家に住んでいる事自体が不法侵入であると言うのだ。
(以下:抜粋「サンダー・マグとの会話」)
「ここに住んではいけないのです。」とミスタ・フォレストは言った。
「この家にいては健康を害します。ゴキブリでいっぱいなんですから。」
「ここに住んではいけないのです。」とミスタ・フォレストは言った。
「この家にいては健康を害します。ゴキブリでいっぱいなんですから。」
「そんなことはない」ミスタ・サンダーマグは満足そうに言った。
「我々がみんな食べてしまったからね。」
「それはちょっと信じがたいですね。」嫌悪感をうまく隠せないまま、ミスタ・フォレストは言った。
「だが本当の事だ」ゴキブリを思い出して、しなびた腹部をぽんぽんと叩きながらヒヒは答えた。
「我々がみんな食べてしまったからね。」
「それはちょっと信じがたいですね。」嫌悪感をうまく隠せないまま、ミスタ・フォレストは言った。
「だが本当の事だ」ゴキブリを思い出して、しなびた腹部をぽんぽんと叩きながらヒヒは答えた。
「それならばこの家は再び市の所有になります。」
「私は居住権を主張する。」とミスタ・サンダーマグは言い、ドアマットの上にしゃがみこんだ。が、すぐに立ち上がった。マットの毛が尻に刺さったからだった。
「最初にこじ開けて入ったのならそれはできませんが。」
「こじ開けたりはしなかった。」ミスタ・サンダーマグは大いに奸知を働かせて言った。「我々は煙突から入ったんだ。」
「私は居住権を主張する。」とミスタ・サンダーマグは言い、ドアマットの上にしゃがみこんだ。が、すぐに立ち上がった。マットの毛が尻に刺さったからだった。
「最初にこじ開けて入ったのならそれはできませんが。」
「こじ開けたりはしなかった。」ミスタ・サンダーマグは大いに奸知を働かせて言った。「我々は煙突から入ったんだ。」
ミスタ・フォレストは別のアプローチを試みた。「あなたのお誕生日はいつですか?」
「星の流れる夜に生まれた。」できるだけ曖昧に答えようと決めて、ミスタ・サンダーマグは言った。
「ルービーホップ彗星の日に違いない。」とミスタ・フォレストは言った。この種の問答は手慣れたものだった。「とするとあなたはだいたい五歳ですね。日にちは4月1日と記入しておきましょう。つまり」
彼は勝ち誇ったように続けた。
「あなたは未成年者です。市はあなたを保護しなければなりません。」
「星の流れる夜に生まれた。」できるだけ曖昧に答えようと決めて、ミスタ・サンダーマグは言った。
「ルービーホップ彗星の日に違いない。」とミスタ・フォレストは言った。この種の問答は手慣れたものだった。「とするとあなたはだいたい五歳ですね。日にちは4月1日と記入しておきましょう。つまり」
彼は勝ち誇ったように続けた。
「あなたは未成年者です。市はあなたを保護しなければなりません。」
「ところが」ミスタ・サンダーマグは落ち着き払って言い返した。
「ヒヒの数え方では私は三百七十八歳なんだ。年金がもらえるはずだがね。」
すばらしい。
実にすばらしい本でした。
実にすばらしい本でした。
ここしばらく、ずっとかたーいコチコチの本を読んでいたので、「ちょっと息抜きに」と思って手に取った本だったんだけど、そういう時に期待通りのものに出会う事ほど嬉しい事はない。
「ヒヒを通して人間の浅ましさを表現する」などといったありふれたトリックなんかじゃ全然なくて、
そこにある「一人のヒヒ」としてミスタ・サンダーマグは物語の中に生きている。
それが実にいきいきとしていて言葉の表現どれをとっても的確で、冷静で且つユーモアがあふれている。
そこにある「一人のヒヒ」としてミスタ・サンダーマグは物語の中に生きている。
それが実にいきいきとしていて言葉の表現どれをとっても的確で、冷静で且つユーモアがあふれている。
寓話といえばそうなのかもしれないけど、「寓話」って言うと「ヒトの言葉を喋るヒヒ」だけがクローズアップしちゃって、せっかくのウィットに富んだ会話の数々、それぞれのシーンがかき消されちゃうような気がしてならない。
この本の魅力はけして寓話的発想だけじゃない。
この本の魅力はけして寓話的発想だけじゃない。
(レストランで:以下抜粋)
しばらくするとウェイターはミスタ・クラップトラップのムニエルとバナナを一房もってきた。
バナナはミスタ・サンダーマグの前に置かれた。
しばらくするとウェイターはミスタ・クラップトラップのムニエルとバナナを一房もってきた。
バナナはミスタ・サンダーマグの前に置かれた。
「これはいったいなんだね。」とヒヒは言い出した。一触即発の態だった。
「あなたは多分バナナの方がすきなんじゃないかと思いまして」
「あなたは多分バナナの方がすきなんじゃないかと思いまして」
「俺は舌平目のムニエルを注文したんだぞ」ミスタ・サンダーマグが怒りに顔を赤くして叫んだ。
そして彼は鼻を鳴らした。「無能なやつめ。サバンナではバナナなど取れないというのに」そう言って交換してもらった舌平目のムニエルに彼は舌鼓を打った。しかしひどく腹を立てていたのでミスタ・クラップトップがしてきた唇音と摩擦音に関する多くの質問に対して答えることが出来なかった。その上、喉頭に触らせて欲しいという彼の申し出も拒否した。
そして彼は鼻を鳴らした。「無能なやつめ。サバンナではバナナなど取れないというのに」そう言って交換してもらった舌平目のムニエルに彼は舌鼓を打った。しかしひどく腹を立てていたのでミスタ・クラップトップがしてきた唇音と摩擦音に関する多くの質問に対して答えることが出来なかった。その上、喉頭に触らせて欲しいという彼の申し出も拒否した。
大人が書いた、大人のための大人な童話。
そんな空想世界は深い感受性と、婉曲な表現力の見事なまでの結集。
そこはかとない芸術性を感じずにはいられません。
そんな空想世界は深い感受性と、婉曲な表現力の見事なまでの結集。
そこはかとない芸術性を感じずにはいられません。
最高でした。